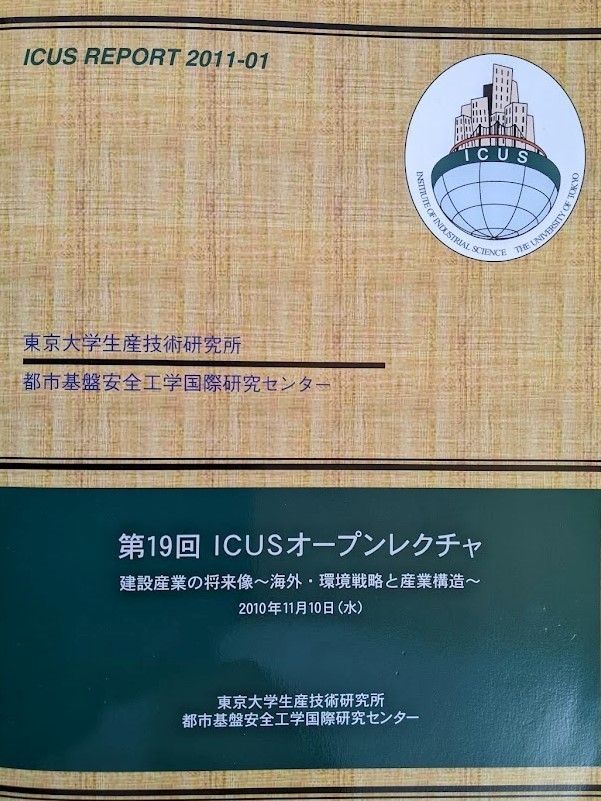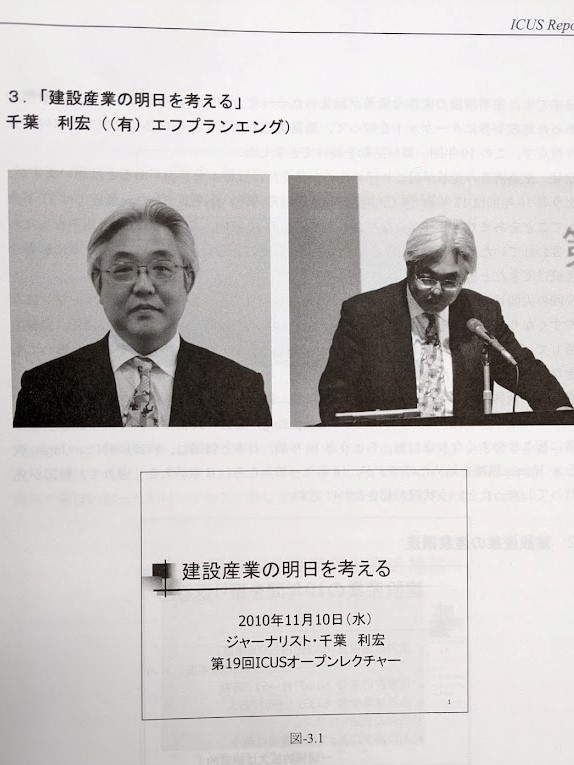●「孤独死や闇バイト」住宅を危険から守る最新技術…「スマートライフ」サービスで豊かな暮らしになるか(2025/03/16)
●米中に出遅れ「日本のスマートホーム」普及のカギ―データ連携サービスで大企業がタッグを組む訳(2025/03/05)
●バブル回避へ日本の住宅政策が採用すべき視点―「年収倍率」はついに10倍を突破(2025/01/10)
<2024年>
●「2024年問題」ドライバー不足を救う驚きの仕組み―フィジカルインターネットは物流危機を解決するか(2024/10/14)
●建設業の深刻すぎる「人手不足」解消に必要なこと―一括請負方式の生産システムを見直せるか(2024/09/22)
●建設業で若者が職人になりたがらない根本原因―仕事量で給与が変動する不安定な給与形態(2024/09/21)
●「日本流の戸建て住宅」がアメリカで売れる理由―積水ハウスと住友林業・大和ハウスで戦略に違い(2024/07/07)
●部屋探しの「不動産ポータル」が役割を終える日―生成AIの活用が加速、「AI不動産」の現実味(2024/04/17)
<2023年>
●都心再開発で日本の国際競争力は上がるのか―東京の分譲マンション平均価格は1億円を突破(2023/11/20)※
●神宮外苑だけじゃない「東京圏のスタジアム問題」―需要を見据えた長期的ビジョンや全体計画が必要(2023/11/09)
●大阪万博「工事遅れ」背景に施工能力不足の深刻―大規模災害の復旧復興への対応をどうするか(2023/09/07)
●日本の既存住宅「省エネ対策」が遅れる残念な事情―データスペースエコノミー時代のデータ戦略(2023/02/11)
<2022年>
●平気でネット通販する人が知らない「2024年問題」―タイムリミットが迫る物流危機を回避できるのか(2022/12/09)
●「ゼネコン新局面」不動産開発ビジネスの焦点―危機の教訓を経て、提案力が必要な時代に(2022/09/12)※
●東京ドームの「顔認証」実際使ってわかった不便さ―入場時は顔パスでも再入場時は紙チケにハンコ(2022/06/02)
●不動産会社主導の「公園再開発」に欠けている視点―神宮外苑“幻の再整備計画"のキーマンを直撃(2022/05/26)
●神宮外苑「樹木伐採」再開発の前にあった幻の計画―複数の公園を「緑のネットワーク」でつなぐ案も(2022/05/24)
●日本の住宅設備「デジタル化が進まない」根本原因―「スマートホーム」が本格普及しない理由とは(2022/02/10)
●部屋探しで「オトリ物件」が排除される驚きの未来―「不動産ID」が導入された不動産業の将来を予想(2022/01/20)
<2021年>
●マンション修繕費問題「ドローン」が救う納得の訳―人手に頼ってきた点検・維持管理をDX化する技術(2021/09/29)
●大和ハウス、デジタル化で挑む売上高10兆円の壁―ハウスメーカーの雄は建設業をどう変えるのか(2021/07/28)
●マンション価格「人工知能の査定」が高精度なワケーデジタル化の遅い不動産業界でAIが本格普及へ(2021/07/15)
●愛知県西尾市、泥沼化した「PFI事業見直し」の行方―4年前から協議進まず再び選挙へ突入のワケ(2021/06/08)
●不動産登記「オンライン申請」実践して見えた課題―どこまで行政手続きの電子化を進められるか(2021/05/31)
●「出社削減」その先に起こるオフィスの大変化―「5G」と「AI」が今後のオフィスづくりのカギに(2021/04/23)
●コロナ禍の「自宅DIY」に立ちはだかる意外な壁―求められる「住宅履歴」の適切なメンテナンス(2021/01/11)
●重要度が増す「防災」意識―「水害ハザードマップ」に注目(2021/01/08)※
<2020年>
●脱ハンコの先「都市のデジタル化」で来る大変化―日本で進む「スマートシティ」実現への取り組み(2020/10/19)
●GAFA対抗「日本型スマートシティ」に勝算あるか―人口増加を見込む「世界の都市」へ売り込む作戦(2020/10/17)
●日本が「都市のIT化」で世界に遅れた苦い事情―「スマートシティ」が日本で実現しなかった訳(2020/10/15)
●建設職人324万人「就労管理構想」の高すぎる壁―行政主導で開発した大規模システムで混乱(2020/09/30)
●住宅リースバックがにわかに活気づいている訳―自宅をいったん売却して賃貸する資産活用法(2020/06/05)
●不動産の「来店不要取引」がいま俄然注目の訳―普及局面に加え、新型コロナでも注目されるか(2020/02/24)
<2019年>
●埼玉「芝川」氾濫も大半の住宅が難を逃れた背景―台風19号の増水で見沼たんぼが果たした役割(2019/10/31)
●「空き家数」の増加にブレーキがかかった不可解―5年前比で空き家率は0.1%増にとどまった(2019/05/10)
●施工品質が「人」によって左右される大問題―建設現場の「技術の見える化」が必要な理由(2019/04/28)
●建設現場の外国人「処遇改善」で日本人と大差―建設キャリアアップシステムで何が変わるか(2019/04/15)
<2018年>
●BIMは不適切コンサル問題の救世主か―3Dの建設設計図で「見える化」(2018/11/30)※
●首都圏で地盤が不安な地域は一体どこなのか―想定外の災害に備えリスクを調べておこう(2018/09/18)
●ハザードマップ超活用法―災害リスクから家を守る(2018/09/14)※
●「木造」にプレハブメーカーが参入する事情―プレハブ工法のコスト低下にも限界がある(2018/08/31)
●日本の戸建住宅を襲う「ガラパゴス化」の懸念―規格バラバラ「プレハブ住宅」のシェアが低下(2018/08/30)
●ニュー新橋ビルのすぐには解決できない悩み―多数の区分所有が耐震強度不足問題を複雑に(2018/05/04)
●六本木ロアビルが姿を消さざるを得ない事情―東京都の耐震強度不足ビル「実名公表」の波紋(2018/04/25)
●高級物件狙う外国人投資家の事情―観光兼ねた投資ツアーが人気(2018/04/14)※
●将来5割減?「オフィス」に迫り来る構造変化―不動産大手がベンチャー支援を始めるワケ(2018/04/03)
●東大閥が産官学すべてを牛耳る―建築・土木の人脈を徹底解剖!(2018/02/10)※
●ソフトバンクの狙いは?―日建設計、パシコンと提携(2018/02/10)※
●業界期待のPFIに暗い影―契約後に相次ぐ計画見直し(2018/02/10)※
<2017年>
●賃借と購入の損得―本当のコストで比較(2017/08/05)※
●地域とつながるサ高住―地方移住という選択(2017/08/05)※
<2016年>
●「解散」時代―老朽マンション(2016/12/14)※
●タワーマンション―実は危ない(2016/12/14)※
●田畑・山林の相続―放置なら将来に禍根も(2016/12/14)※
●ゼネコンの未来を変える「3D改革」の衝撃―鹿島、大幅増益の知られざる立役者(2016/07/29)
●労働者育成も“丸投げ" 根深い重層構造―施工不良の真因(2016/07/23)※
●ICTがゼネコンを救う?―公共工事で急速に活用が進みだした(2016/07/23)※
<2015年>
●マンション流通革命の前に立つ業界団体の壁―不動産価格推定サービスは波を起こすか(2015/11/19)
●傾きマンション事件が起こるのは必然だった―民間建設工事にも問われる発注者責任(2015/10/27)
●だから日本の中古住宅はいまだに買いにくいー政府肝いりのリフォームローンが不調なワケ(2015/08/06)
●だから日本の中古住宅は一向に活性化しない―空き家問題の遠因にも?「物件囲い込み」の愚(2015/06/09)
●神宮外苑開発が試金石―五輪レガシーをどう作る(2015/05/16)※
●大手も駆け込む長谷工の施工力―受注シェアは一段と上昇(2015/05/16)※
●セレブを狙い撃つマンション規約改定の衝撃―紛糾した「コミュニティ活動条項削除」の意味(2015/04/09)
●鹿島と大成建設、トップ交代に残された宿題―"大政奉還"は先送り、日建連会長は誰に?(2015/02/26)
●職人軽視の日本人が、建設業をダメにするー夢や誇りを持てなければ若者は集まらない(2015/02/01)
●建設労働者の処遇改善が一向に進まないワケー10年がかりで取り組むプロジェクトの弱点(2015/01/29)
●ゼネコンが自らの手で招いた「建設業の衰退」―外国人を入れても職人不足は解消に向かわず(2015/01/27)
<2014年>
●その日、三菱自動車の社長は来なかった―「抜擢人事」の後に起きた裏面史を綴る(2014/12/31)
●日産「セフィーロ」が獲った“幻”の特賞―20年前に起きた「事件」の真相を明かそう(2014/12/29)
●知られざる、もう一つのカー・オブ・ザ・イヤー―自動車業界も注目した「あの日」を回顧(2014/12/27)