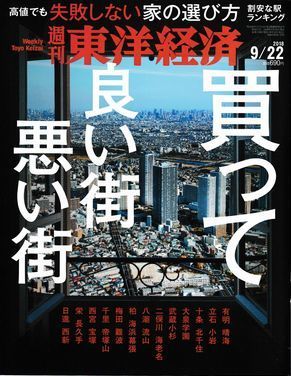週刊東洋経済の特集「買って良い街悪い街」に、ハザードマップに関する記事「首都圏で地盤が不安な地域は一体どこなのか―想定外の災害に備えリスクを調べておこう」を提供した。東洋経済オンラインにも転載されたのでお読みください。特集の主旨が「失敗しない家の選び方」なので、ハザードマップの使い方にポイントを絞ったために泣く泣くボツにした話も多かった。記事に盛り込めなかった話を中心に、ブログ「未来計画新聞」にまとめておく。
利便性よりも地盤の安全性?
2011年3月の東日本大震災の直後に、未来計画新聞に「安全・安心な家づくりを考える(全4回)」と題したコラムを掲載した。最初に「第一歩は土地選び」と書いたが、その時の考え方は今でも全く変わらない。
いくら都心に近い便利な立地だとしても災害リスクの高い土地に住むぐらいなら、不便でも安全な土地に住むというのが筆者の考え方だ。利便性や将来の資産価値を考慮して都心に近くて通勤に便利な駅近の立地を選ぶことを勧める人は多いが、わざわざ災害リスクの高い土地にインフラ整備のための多額の税金を払って住もうとは思わないだけである。
さいたま市緑区東浦和に土地を購入して自宅を建てたのは1999年のこと。どのようなプロセスで土地を選んだのかはコラムの2回目に詳しく書いた。2400年以上前に創建されたといわれる武蔵一宮氷川神社がある「大宮台地」の南端に位置しており、駅からの距離よりも地盤優先で購入した。
当時は、地盤や地形にこだわって土地を選ぶという話をあまり聞いたことはなかった。しかし、2008年からNHKで放送が始まった番組「ブラタモリ」の人気が出て、2015年からはレギュラー放送が始まった。岩石や地形・断層の話や「何でもキワが面白い」といったマニアックな話が受けているようなので、結構、世の中には地盤や地形に関心のある人が多いのではないかと思っている。
下水処理能力と想定降雨量の関係は?
最近ではゲリラ豪雨が発生するたびに、道路が冠水したり、下水管から雨水があふれたりするニュースがテレビに流れ、深刻な浸水被害が発生するケースが増えている。
原稿締め切りの10日ほど前の8月27日のゲリラ豪雨で「世田谷区深沢で車が水没する被害に会った」という話を聞いたので、リアリティのある題材として使わせてもらった。実際に世田谷区のホームページに掲載されている洪水ハザードマップを見ると、呑川沿いの世田谷区深沢は浸水被害が発生する地域となっている。
国土交通省が、堤防や下水道などのハード対策に加えて、洪水浸水想定区域図作成マニュアルを策定してソフト対策に乗り出したのは2001年からだ。Aさんが購入した1997年当時は洪水ハザードマップは作成されておらず、世田谷区版が公開されたのは2006年である。
東京都では、これまで50ミリの雨水処理に対応できるように下水道整備を進めてきたが、洪水ハザードマップは2000年の東海豪雨で記録した114ミリ/時間を想定して作成されている。東洋経済の記事では「想定外の災害に備えよう」という見出しが付けられたが、今回の110ミリのゲリラ豪雨で呑川沿いの地域では「想定通り」の浸水被害が発生したわけだ。
もちろん浸水被害を軽減するための対策も進められている。Aさんが最初の浸水被害に会った2014年7月のゲリラ豪雨のあと、東京都下水道局では2020年度の向けた新たな経営計画を策定。とくに浸水被害の大きかった「世田谷区深沢・目黒区八雲」「目黒区上目黒・世田谷区弦巻」「大田区上池台」「文京区千石・豊島区南大塚」の4地区で、75ミリ対応の処理能力増強工事に着手した。完成すればハザードマップの被害想定区域の縮小も期待できる。
一方で、2015年の水防法改正で、ハザードマップの作成基準が「想定し得る最大降水量」に引き上げられたため、東京都では想定降水量を114ミリから153ミリに引き上げて改定を進めている。2018年3月には神田川流域の改訂版が公開され、今後、他の地域でもハザードマップの改定が行われる予定だ。現在のマップでは安全と思われている場所でも、最新版では被害想定区域となる可能性もある。
ちなみに東京都の下水道は、8割が家庭からの排水と雨水を同じ下水管に流す「合流式」。大量の雨水が下水管に流れ込むと、場合によっては住宅に下水が逆流する可能性もある。かつて世田谷区あたりでも畑が多く、雨水の50%以上は地面に浸透して処理できていたが、現在はアスファルトやコンクリートで固められて雨水の80%が下水管に流れ込む。雨水浸透処理能力の低下も、浸水被害拡大の原因となっているようだ。
老朽化が進む宅地擁壁の安全性は?
今回の取材では、国土交通省の国土地理院のほかに都市局都市安全課にも話を聞いたが、残念ながらカットせざるを得なかった。
現在、国土交通省が所管しているハザードマップは、「洪水」や下水道の排水能力を超えた浸水被害を示す「内水」のほかに「高潮」「火山」「津波」「土砂災害」「震度被害(揺れやすさ)」「地盤被害(液状化)」の計8種類がある。国交省で策定したマニュアルに基づいてハザードマップを作成するのは各自治体だ。
国土地理院が作成している「重ねるハザードマップ」は、自治体からデータをもらって重ねられるように加工したうえで公開している。かなり大変な作業のようで、最初から重ねることを前提に標準化できれば良いのだろうが、どうも簡単ではないらしい。マニュアルの段階で、重ねることを想定した仕様になっていない可能性もある。国土地理院のおかげで、地盤ネットなどの民間会社が利用しやすいデータが整備されている。
都市局の都市安全課では、宅地の耐震化に取り組んでいる。国交省では、2006年から大規模盛土造成地マップを作成して公表するように地方自治体に求め、公表状況を定期的にまとめている。今年(2018年)7月に公表した資料によると、公表率は初めて60%を超えたが、680市町村では未公表となった。
原稿の締め切り間際の9月6日には、北海道胆振東部地震が発生し、札幌市清田区里塚地区などで液状化被害が発生した。札幌市の液状化危険度マップを見ると、確かに札幌市清田区の里塚周辺は災害リスクが高い地域と表示されていた。札幌市では大規模盛土造成地マップも公表しており、里塚周辺には大規模に盛土した2か所の造成地が示されていた。
大規模盛土造成地は、盛土の危険度を示すものではないが、ハザードマップとして公表している自治体も47団体もあり、消費者としても注意すべき情報だろう。ただ、大規模盛土造成マップの公表率がゼロの都道府県が、栃木、石川、島根、山口、佐賀、熊本、鹿児島、沖縄の8県もあり、首都圏では千葉県が9.3%と低い。
2016年4月に発生した熊本地震では、宅地擁壁や大規模盛土造成地の崩壊、液状化被害の発生で、約1万5000件の宅地が被災した。都市安全課では、今年7月に「宅地耐震化ガイドライン」を初めて提示し、復旧時と通常時に分けて取り組むべき事項を整理した。
高度経済成長期に造成された宅地も50年が経過して擁壁の老朽化が進んでいる。宅地擁壁の所有者は、擁壁の上に住んでいる人であるが、擁壁の老朽化で危険を感じるのは擁壁の下に住む人だろう。景色の良さが気に入って高台に住む人も少なくないが、擁壁の耐震化をどう推進していくかが今後の課題となっている。