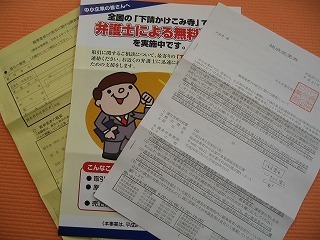
記者も「職人」と同じ労働者
大工の家に生まれた私は「記者」という職業をホワイトカラーというより、記事づくりをする「職人=労働者」に近いと思ってきた。いろいろな事情があって新聞社を辞める決断をしたときも、メディア業界で「職人」だけでは食っていけないことも判っていた。自分なりの準備をしたつもりだったが、想像していた以上に厳しい現実が待っていた。
実は、自分以外のフリーのジャーナリストの実情をそれほど知っているわけではない。日本不動産ジャーナリスト会議の諸先輩も、大手新聞社を定年退職して年金収入があるか、既存媒体に所属して給与がある人がほとんど。本が売れてテレビのキャスターやコメンテーターになれれば、十分な収入が得られるのだろうが、新聞や雑誌に記事を書いているだけなら、定期連載を含めてかなりの本数を書いている売れっ子でなければ大変なはずである。
かつては、自らメディアを立ち上げた先輩記者もいるが、いまや新聞や雑誌などの既存メディアは完全に不況業種になってしまった。4年ほど前に、雑誌編集者から新しいWebメディアを立ち上げたカフェグローブ・ドット・コムの矢野貴久子社長をインタビューしたことがあるが、メディアに物販、広告、マーケティングを組み合わせた新しいビジネスモデルで、矢野さん自身はもう編集者を卒業して経営者となっていた。
下請じゃ、いつまで経っても食えない?
「どうしたら”職人”で食っていけるのか?」―いろいろと試行錯誤してきたが、私の実力不足・努力不足もあってか、なかなか思うようにならない。多くの人に相談しても、「一人じゃ限界がある。まとまって仕事を請け負えるように事業化するしかないよ」と、似たようなアドバイスが返ってくる。
まとめて仕事を請ければ、確かに金額は大きくなる。しかし、仕事が大きくなれば、従業員を雇うか、自らも下請を使わざるを得なくなる。当然、元請としての利益を取って仕事を分割する。自分の取り分は増えるかもしれないが、元請代金のなかの原稿料そのものを増やせなければ、下請に自分と同じ苦労をさせることになる。
アドバイスの多くは「いつまでも下請のままだから駄目なんだ。元請になってピンはねしなきゃ、儲からないよ」と言っているのも同然なのである。
「人間社会だって、弱肉強食の世界なんだから、上に立ったものが儲けるのは当然だ」―企業経営者の多くはそう答えるかもしれない。しかし、元請が儲けるのと、下請を泣かすこととは全くの別問題だろう。従業員や下請に適正な報酬を支払った上でなら、いくら企業経営者や元請が儲けても誰も文句は言うまい。
非効率な下請の重層化がなぜ進む?
いまや日本社会において、建設業界だけでなく、ITやメディアなどあらゆる業界で重層下請構造が浸透している。その先駆けとなった建設業界では、1970年代に入って下請構造の重層化が進みだしたと言われる。学術的に検証したわけではないが、私は1966年に「官公需法」が施行されたことが大きく影響したのではないかと考えている(小冊子「産業比較:情報サービス・ソフトウェアvs建設業」で考察)。
官公需法は、中小業者でも「元請になれば儲かる」ことを前提としたような法律である。もちろん法の精神が企業の「元請志向」を増長させるものではないとは思うが、利益率が高かった(今では儲からなくなったようだが…)公共工事・公共調達を元請けできるチャンスが法律で認められたわけである。誰もが少しでも儲けを増やそうと元請志向を強めるのも当然だろう。
もちろん元請志向や官公需法が悪いと言っているわけではない。元請としての付加価値分と元請が負うリスク分を適正に取り分として得ているのなら、問題はないのだろう。しかし、元請の取り分が適正かどうかは誰も検証できないし、実際に日本では”下請けイジメ”など適正な下請取引が行われているとは言い難い状況にある。元請ばかりが増えて下請構造の重層化が進むと、経済活動全体から見て非効率であるのは明らかだ。
職人が誇りを持って仕事に取り組める社会
私は、子どもの頃、職人たちに囲まれて育ってきた。それも影響しているのだろうが、日本が「ものづくり」立国だと言うのなら、職人が誇りを持って仕事に取り組める社会であるべきだと考えている。ところが、職人たちにとって今の日本社会は住みにくくなる一方のように思える。
私が建設業の構造問題としてゼネコンに厳しい見方をしてきたのも、元請ばかりが増えすぎて、そこで働く職人たちに適正な報酬が配分されていないのではないかと危惧してきたからだ。ゼネコンにコストの透明性を求めるのも、発注者への配慮というより、実は適正な労務費が確保されているかを心配するからである。
昨年9月のリーマン・ショック以降、日本でも雇用削減の嵐が吹き荒れている。派遣労働者ばかりでなく、正社員にも人員削減が広がって、メディアでも雇用のあり方に関する議論が活発化している。それ以前に、日本に根深く浸透しているピンはね体質を是正しなければ、いくら雇用制度を変えたところで問題は解決しないのではないだろうか。
(づづく)



